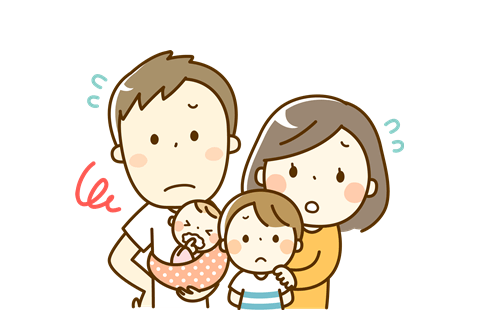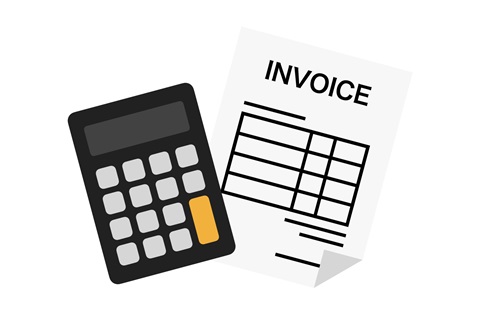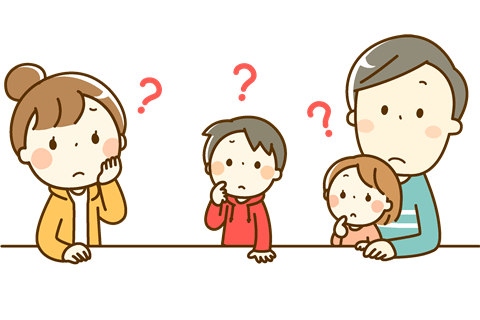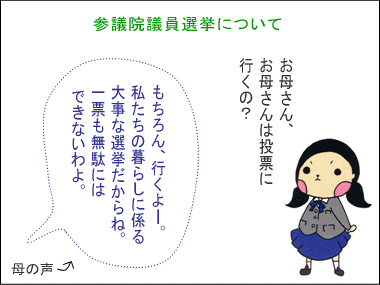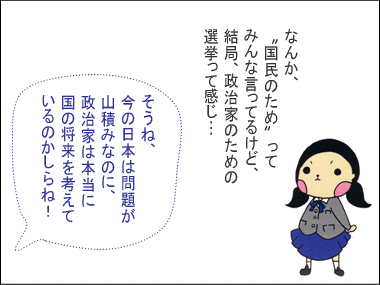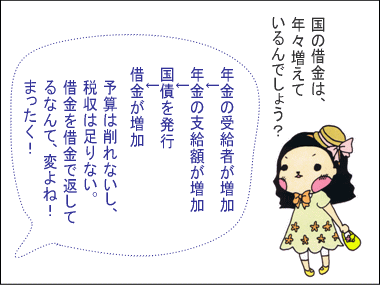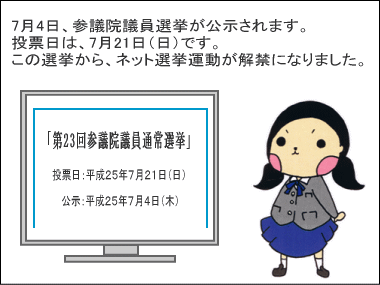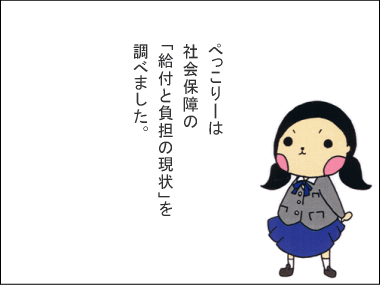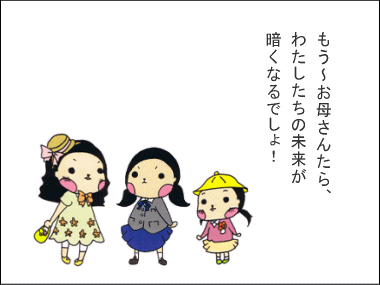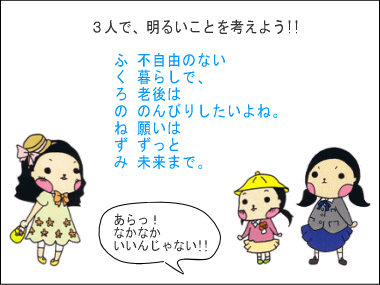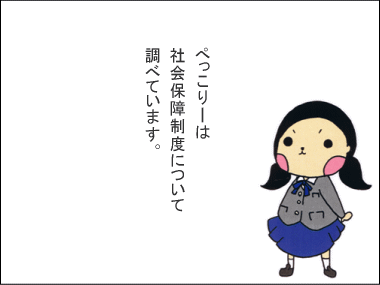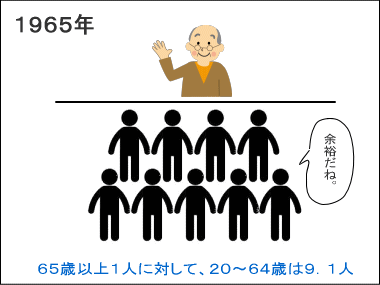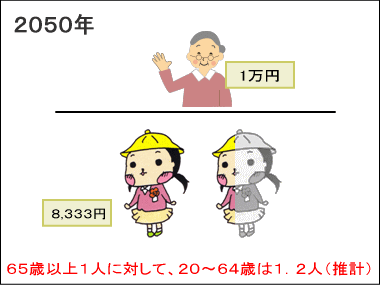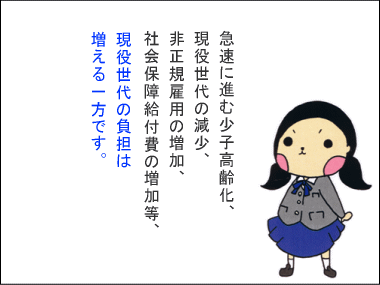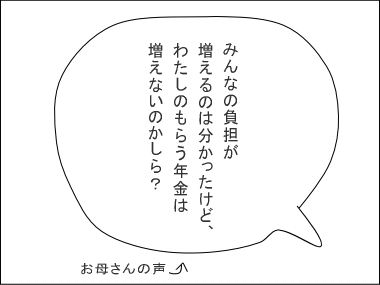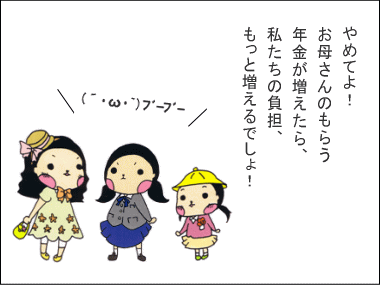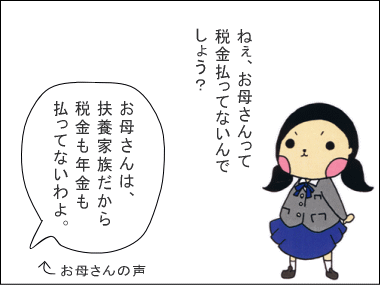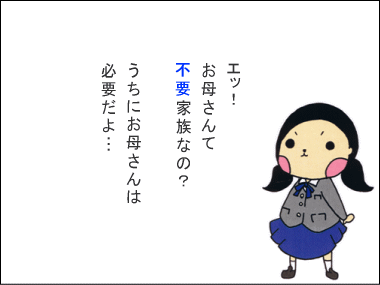ネットを見ていたら、マネーポストWEBのこんな記事がありました。
10月に導入されたインボイス制度には、免税業者との取引によって、国(地方分を含む)に消費税率10%以上の税収が入ってくる「消費税二重取り」の仕組みがある。
というものです。
そんなことが起こるのか??
計算をしてみると、確かに「二重取り」と言っていいのか分かりませんが、消費者が負担した消費税額よりも多く納付するケースがありました。
記事にも書いてありましたが、例えば
材料業者(A)→生産業者(B)→小売業者(C)→消費者の取引で
生産業者(B)が免税事業者の場合、
小売業者(C)は(B)からの仕入れに対して仕入税額控除ができないため消費税を丸ごと納めなければなりません。
| |
材料業者(A |
生産業者(B) |
小売業者(C) |
事業者が個別に納付した消費税の合計 |
| 商品価格+消費税額 |
10,000+1,000 |
15,000+1,500 |
22,000+2,200 |
|
| 事業者が納付した消費税 |
1,000 |
1,500‐1,000=500 |
2,200-1,500=700 |
2,200 |
| (B)が免税事業者の場合の納税額 |
1,000 |
0 |
2,200 |
3,200 |
なるほど、適格請求書がないと仕入控除ができないだけの問題だと思っていたら、こんなことが起こるんですね。
消費税とはどんなものかおさらいしてみましょう。
消費税は「消費者が負担して」「事業者が納付する」税金です。
消費税の基本的は計算方法は、「売る時に預かった消費税」と「仕入れる時に預けた消費税」の差額を納める仕組みです。
インボイス導入前だったら、小売業者(C)は仕入税額控除ができたので、700円を納めればよかった。
そして500円は、生産業者(B)の益税となり、国から見ると、消費者が負担した消費税をきちんと回収できていなかったことになります。
| |
材料業者(A) |
生産業者(B) |
小売業者(C) |
事業者が個別に納付した消費税の合計 |
| 商品価格+消費税額 |
10,000+1,000 |
15,000+1,500 |
22,000+2,200 |
|
| (B)が免税事業者の場合の納税額 |
1,000 |
0 |
2,200-1,500=700 |
1,700 |
実際、消費者は10%分の消費税しか払っていないので「二重課税ではない」わけですが、誰かが余分に納めることになります。
全員が課税事業者になればこの問題は解決されますが、この先どうなるのでしょうか。
何にしてもややこしい制度ばかりです。